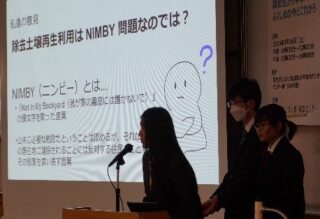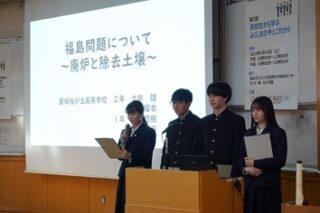テーマ
1.「第2回 高校生と学ぶ ふくしまの今とこれから」開催報告
2.ALPS処理水に係る海域モニタリング情報
—————–
ふくしまの食相談センターでは、2024年3月16日(土)、東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、「第2回 高校生から学ぶ ふくしまの今とこれから」を開催しました。福島県から相馬農業高校、磐城桜が丘高校、安積高校、橘高校の4校と東京都立戸山高校、帝京大学、慶応義塾大学、東京すし和食調理専門学校の全8校の学校を招き、100名を超える参加者によって、福島の復興に向けた活発な意見交換が行われました。
—————–
◇開催概要
午前の部(10:00~11:30)
【特別講演】 三好あさぎ氏 在カンボジア日本国大使館
「国際社会」を相手にする仕事を通じて
福島県出身の在カンボジア日本国大使館に勤務する三好あさぎ氏にカンボジアからオンラインで講演いただきました。三好あさぎ氏は、高校2年生まで福島県立福島女子高校(現、橘高校)に在籍。2022年から23年にかけてEUの輸入規制撤廃に尽力されました。現在はカンボジアの日本大使館で日カンボジア外交の仕事をされています。今回は、Zoomでカンボジアと日本の会場を繋ぎ、1時間の講演と30分の質疑応答を行いました。外務省職員として行ったEUとの輸入規制撤廃に向けた交渉や現在のカンボジアでの外交官としての仕事など、普段耳にすることができない貴重なお話を伺うことができました。その後の高校生からの様々な質問にも真摯に答えていただき本当に素晴らしい講演でした。
【三好氏講演会】 【参加した高校生】
午後の部
第1部 高校生の学習発表(13:00~14:20)
5つの高校(6グループ)が登壇し、それぞれの学習成果を発表しました。
(1)福島県立相馬農業高校 「郷土芸能の継承と各科のイノベ学習」
生徒全員が参加する郷土芸能保存活動やイノベ学習など、さまざまな取組をしています。また、「地域に元気を発信」を合い言葉に、地域と共に歩み続けるという発表でした。
(2)福島県立橘高校 「高校生が“挑戦”するための機会創出プロジェクト」
福島の高校生としてもっと福島を知り、これからについて考えていくことが必要だが、普段の学校生活の中ではなかなか難しい。これからの予測不能な社会に対応するためには、「自ら考えて行動する力」を育む、校外活動や地域一体型の探究活動が必要ではないかと考え、高校生主催のイベントの企画や福島を知るための取り組みを提案しました。
(3)福島県立磐城桜が丘高校
①家庭クラブ「さくら色の架け橋2024」
復興の視点から活動範囲をいわき市だけでなく福島第一原子力発電所のある浜通り地域に広げ、「楢葉町さつまいもプロジェクト」の活動を行っています。地産地消や風評被害の払拭の架け橋として、部員が自ら育てた「ふくしまゴールド」という品種のさつまいもを使ったお菓子を、地元スーパー「マルト」と共同開発して販売しています。そのうちの数品を試食品として会場の参加者に提供いただきました。
②科学部「福島問題について~廃炉と除去土壌~」
汚染水やALPS処理水、除去土壌問題を取り上げ、「地元や国民の理解を得るためには東電・国と住民の信頼形成が必要であること、一方的でない誠実な情報提供や対話が必要であること、また、電気を使っている人はもっと関心を持つべきであること」などについて発表しました。
(4)福島県立安積高校 「除染土壌再生利用と福島復興」
除去土壌の再生利用について学び、発信することをテーマに学習しており、県外では再生利用さえ受け入れの見通しがたたない現状において、「福島が最終処分を引き受ければ除去土壌の再生利用が進むのではないか」と提言。除去土壌の再生利用が進まない理由として、それが必要な施設だと知ってはいるが、自らの居住地に建設することには反対する「NIMBY」(我が家の裏庭にはおかないで)を紹介し、私たち全員が除去土壌について正しく理解すべきではないかとの考えのもと、まずは会場の皆さんが考えて欲しいとして、隣同士の席の人同士で話し合い、その後、発表をしました。
(5)東京都立戸山高校 「除染土壌問題の認知度をあげる方法」
除去土壌を受け入れる側の福島県外の学校として、除去土壌の再生利用についての理解や認知度が低いことを、自分たちが行ったアンケート結果に基づき発表しました。戸山高校では、20代から60代、高校生を2グループに分けてアンケートを取り、その分析結果から、高校生は「多くの情報を受け止めているが判断が出来ない」と回答する人が多く、大人は「除去土壌事業は危ないからやってほしくない」と回答する人が多いことなど、両者の違いを分析。いずれも除去土壌について理解した後は「近くにあっても問題がない」という回答者が増えることから、除去土壌事業については正しい理解が必要と提言。講演会や学校教育を通じて、正しい情報を伝えることが重要、と発表しました。
【発表風景・磐城桜が丘高校】 【発表風景・安積高校】
第2部 ポスターセッション(14:30~15:00)
高校5校、高校協働企業1社、大学2校、専門学校1校、環境再生プラザ、全国消費生活相談員協会が、それぞれの活動をポスター展示。参加者は各自が興味を持つテーマのブースに立ち寄り、熱心な意見交換を行いました。30分では足りないくらい多くの質疑応答がありました。
【ポスターセッションの様子】
第3部 高校生・大学生・専門学校生と対話しよう(15:00~15:55)
参加校から各2名が登壇し、参加者や登壇者からの質問に答え、熱心な対話が交わされました。
①慶応義塾大学、帝京大学、東京すし和食調理専門が学校の研究・活動紹介
②大学生、専門学校生から高校生の学習発表およびポスター展示について感じたことをコメント
③会場内(登壇者も含む)の参加者からの質問に対して、登壇者がそれに答える対話セッション
【パネルディスカッションの様子】
◇参加者からの感想等
参加者からは、「感銘を受けた」、「刺激をもらった」等の好意的な感想が多く寄せられました。参加者アンケート結果は以下の通りです。
・参加者の満足度は大変高かった。
・印象に残ったプログラムは、「高校生による学習発表会」が最も多かったが、その他のプログラムへの関心も高く、どのプログラムも好評だった。
・自由意見および感想欄には、「高校生の学習発表会に感銘を受けた」、「交流会での活発な意見交換を見て若者への期待感が高まった」、「ポスターセッションは時間の制約があったが、もっとじっくり聞きたかった」などの声があった。
—————–
2.ALPS処理水に係る海域モニタリング情報
2023年度のALPS処理水の海洋放出は、計画通り、全4回安全に実施されました。2024年度は、放出回数を全7回、放出水量約54,600m3、トリチウム放出量約14兆ベクレルを計画しています。環境省では、環境中の放射性物質の状況を確認するための海域環境モニタリングの実施を担っており、環境省に加え、関係省庁等で実施しているトリチウム等に係るモニタリング結果をまとめて掲載しています。
◇海水中のトリチウム
これまでのモニタリング結果は、過去の日本全国の海水のトリチウム濃度の変動範囲内であり、人や環境への影響はありません。
◇水産物・水生生物中のトリチウム
水産庁の分析結果については、全ての結果が検出下限値未満でした。
◇トリチウム以外の核種
周辺海域の過去の変動の範囲内であることが確認されており、人や環境への影響はありません。
◆東京電力HP 福島第一原子力発電所の廃炉の現状と取組みをお伝えします Vol.35
https://www.tepco.co.jp/decommission/effort/pdf/2024/ad_20240428.pdf
◆環境省HP ALPS処理水に係る海域モニタリング情報
https://shorisui-monitoring.env.go.jp/
【編集後記】
2024年度のメールマガジンは、ふくしまの食相談センターで行う勉強会、視察会、展示会、交流会などの情報を隔月でご紹介する予定です。今年度も福島や近隣の風評被害払拭に向け、様々な情報を発信しますので、どうぞよろしくお願いいたします。